【読書記録】”「後回し」にしない技術”の学び
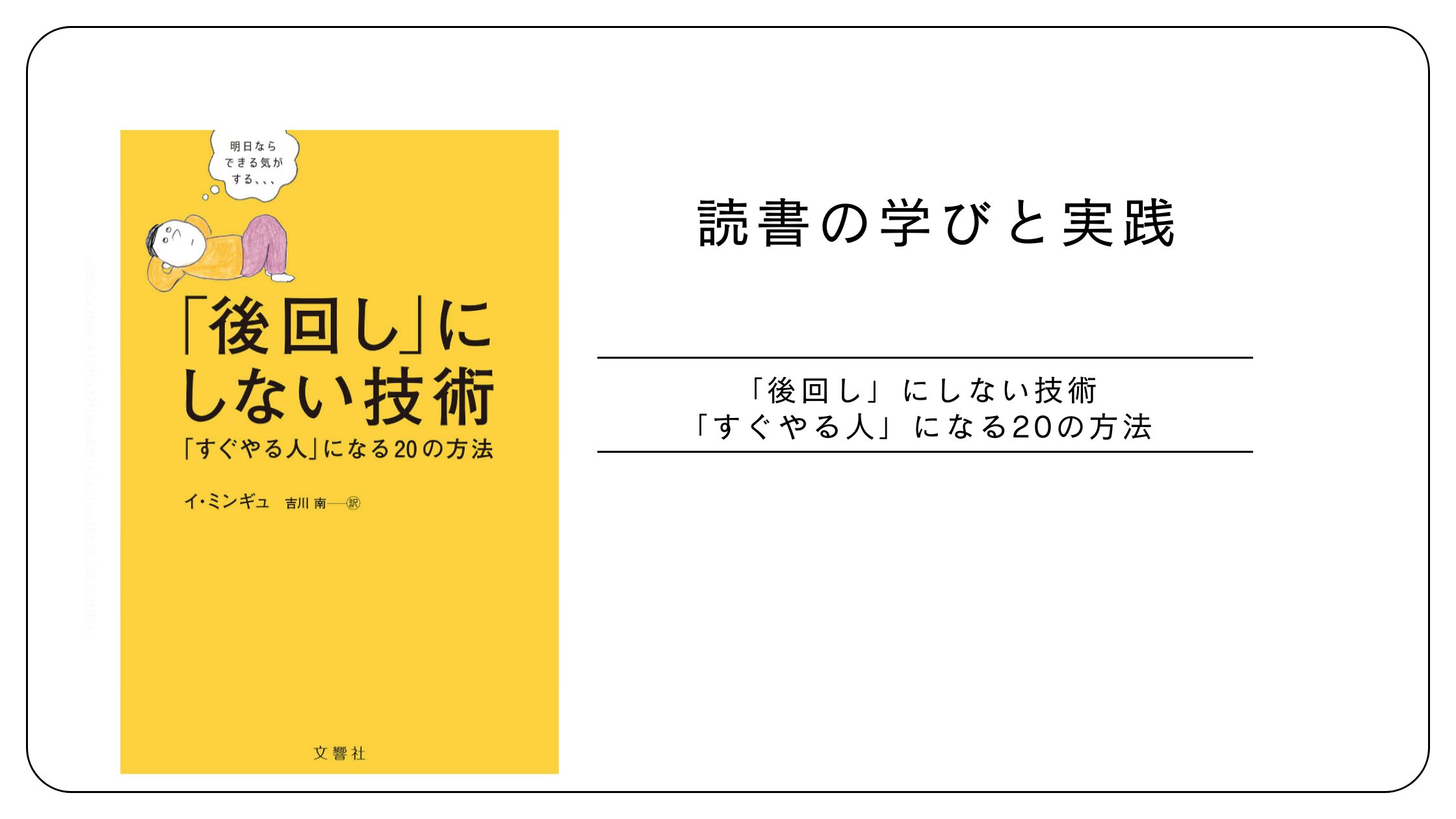
最近読んだ本からの学びや気付いたことをシェアします。
今回の本はこちらです。
“「後回し」にしない技術 「すぐやる人」になる20の方法”
イ・ミンギュ(吉川美南 訳)
イ・ミンギュさんは韓国の心理学者です。
私たちにとって身近な例、日本の会社の例を挙げられており、読みやすいとともに、「韓国でも同じように言うんだ」、という言い回しや格言があって、面白かったです。
- 痒くない方の足を掻いていないか
- ひそかな決心は、決心しないことと同じ
- 人生は「実験」の連続だ
- 「わからない」と言える人は愛される
- 意思の力には頼ってはいけない
- いかなるときも目標から目を逸らさない
痒くない方の足を掻いていないか
これは痒い足を放おっておいて反対側の足をかうという意味で、問題の核心を把握できず、意味のないことに力を注ぐ人を例える使う、韓国のことわざです。
この本質は、”問題を正確に把握できなければ、問題ではないことを解決するために多くのエネルギーと時間を消費する。”ことです。
【問題を解決するためのステップ】
①問題があるという事実を受け入れる =問題の認識
②問題を正しく把握する= 自分に適切な問いを投げかける
③様々な解決策からもっとも効果的な戦略を選び、実行に移す
自分に適切な問いを投げかけるというのは、問いかけを変えて色んな角度から聞いてみることです。
「どうしたら店を大きくできるか?」という問いは「どうしたらもっとたくさん売ることができるのか?」、
「何を言おうか」の問いの代わりに「どうしたら相手の心を動かせるか」という問いに変える。
ある通りがかりの人が、犬と一緒に座っている人に近づき、尋ねた。
「あなたの犬は噛みつきますか?」
男は「いいえ」と答えた。その通行人が手を伸ばして犬をなでようとすると、犬がその手に噛みついた。
彼は起こって男に言った。
「あなたの犬は噛みつかないと言ったでしょう!」すると男が答えた。
「この犬は私の犬ではありません。」――ロバート・P・マイルズ『バフェット 投資の王道』
ひそかな決心は決心しないことと同じ
決心を公開すると叶う理由
決心が曖昧になってしまう大きな理由のひとつは、心の中で密かに誓うから。
様々な研究結果で、人は言葉や文章で自分の考えを公開すると、その考えを最後まで守ろうとする傾向があります。
その理由は、以下の3つです。
① 言葉が私達の行動を決定するから
「私は勉強が好きだ」という言葉を繰り返し口にしていると、いつの間にか自分が勉強家だと考えるようになります。
人は自分の言葉と行動を通じて、自分の態度を判断するようになり、態度は行動を決定します。
だから、言葉を変えると行動を変えるのです。
② 否定的な評価を受けたくないから
人は言っていることとやってることが一致していないことに対して、「内と外が違う」、「無責任だ」などの否定的評価を与える傾向があります。
一方、言葉と行動が一貫している人には、「言行一致」、「信頼できる」、「一貫性がある」、「責任感が強い」という風に、肯定的に評価するのです。
③ ストレスを減らすことができるから
人は自分の言葉と行動が一致しないとき、自己認識に矛盾が生じ、ストレスを受けます。
そこでなんとかして自分の言葉と行動を一致させてストレスを減らし、
精神的安定を求めようとする傾向があります。
目標を公開することのもうひとつのアドバンテージ
決心を公開することが目標達成の助けになる理由が、もうひとつあります。
実行が困難になって途中で諦めたくなった時、決心を知っている友人や家族から援助を受けられるからです。
決心が揺らぎやすいときは、支援を求められる誰かがそばにいると信じるだけでも、大きな助けになります。
決心を「公開宣言」する
自己防御力と実行力が優れた人は、外部の力を活用して自分をコントロールする。公開宣言は、外部の力を利用したもっとも効果的な方法の一つです。
本の中では効果的な公開宣言の5つの具体的な方法を紹介されていましたが、私は3つが特に大事だと思いました。
①できるだけ多くの人に公開する。
②繰り返し宣言する
③はっきり宣言し、約束を守らなかった時に払うべき対価を明らかにする
決心の公開範囲が広ければ広いほど、実行可能性が高くなります。
決心を成功させたければ、特によく見せたい人や体面を守らなければならない人の前で公開すると、人は、自分の言葉に責任を取ろうとします。
公開宣言の回数が増えれば、それだけ決心を撤回する可能性は低くなる。
いつでも逃げ出せるような中途半端なやり方ではなく、抜け出せないような工夫をします。
例えば、禁煙だったら次のような代価を明らかにします。
「私は今日からたばこを辞めました。もし1本でも吸ったら、1000万ウォン(約76万円)を私が一番嫌いな政党に匿名で寄付します」や、
「たばこを辞めました。もし私がたばこを吸うところを見た方がいたら、10万ウォン(約8900円)を差し上げます」とすべての知り合いにメールを送る、これくらい具体的に代価を示します。
人生は実験の連続だ
私がこの本で一番響いた言葉です。
エジソンは、自分の行動を「実験」だと定義し、どんな些細な問題であっても、その解決策を求めるために意図的な努力をしたなら、それを実験だと考えました。
エジソンにとって失敗とは、仮説が間違っていたという事実を教えてくれ、新しい仮説が必要だということを悟らせてくれる、もう一つの成功体験でした。
エジソンは普通の人が「経験(Experience)」と言うところを、「実験(Experiment)」と呼びました。
告白したい相手がいる、説得したい人がいるのに、「恥をかくのではないか」、「言っても無駄だ」と思うなら、その状況を実験だと考える。
しっかり観察して、仮説を立て、解決策を導き出し、実験してみるのです。
この実験精神は3つの点で優れています。
①失敗に対するおそれを和らげる。
実験は失敗を当然と考えます。
もし失敗したとしても、それによって仮説の間違いをきちんと検証できます。
したがって失敗を恐れなくなります。
②創造性が高まる
実験とは、古い知識や理論を新しいものに置き換えることです。。
実験精神を持てば、固定観念が破られ、視野が広くなり、柔軟性と創造性が高まります。
③自分をコントロールできる
実験とは、ある現象をよく観察し、様々な条件を人為的につくって仮説を検証するプロセスです。
そのため、自分自身をよく観察することになり、コントロールできるようになります。
日常の生活から、定期的にいつもと違うパターンの行動を起こす、実験をしましょう。
例えば、いつものテレビを見るという行動の代わりに、読書をする、散歩をする、部屋の明かりを消し、クラシック音楽を聞く、など、違う行動をしてみましょう。
これまでのパターンと違うことをすれば、いくつかの変化が起こります。
生活スタイルがバラエティーに富み、考え方が変わります。
違うアイデアが浮かび、違った結果を得られます。
「わからない」と言える人は愛される
人の助けなしに豊かな人生を送れる人はいません。
望むものを手に入れられなかった
= 他人の助けをうまく得られなかった
= 助けをうまく求められなかった
ということです。
尋ねることでより多くのことを学ぶことができ、時間とエネルギーを無駄にすることないからです。
助けを求めることは、世の中に「実行したい」というシグナルを送るのと同じことです。
尋ねないのは、学びたくないということであり、助けを求めないのは切実に望んでいないのと同じことです。
助言を求める人を嫌う人はいません。
誰かを助け、喜びを感じたことはありませんか?それは他の人も同じなのです。
誰かに助けを求めるということは、それは相手に自分が「価値ある存在だ」と感じる機会を提供することになるのです。
助けを求めるための行動は、次の通りです。
① 自分がどんな努力をしたのかを知らせる
何の努力もせずに人に助けだけを望む人に、手を差し伸べてくれる人はいません。
助けてもらいたい相手に、あなたがしてきた努力とその実践の過程を知らせて、手を貸せば希望があると確認させる必要があります。
助けてもらえないのであれば、相手に助けてやる価値のある人間だと確信させることに失敗したということです。
② 他人と違う態度で助けを求める
助言や手助けを受けるには、相手を尊重しながら、学ぼうとする態度と謙遜の姿勢を持ち、他人と違った方法で近づく必要があります。
③ お返しすることを約束し、フィードバックを提供する
ある研究によれば、ただ頼み事をする場合に手助けを受けられる可能性は25%以下であり、お返しがあることをほのめかすと、その可能性が80%以上に跳ね上がるそうです。
どんな関係であれ、片方だけが利益を得る一方的な関係は長続きしません。
意思の力には頼ってはいけない
すべての生物は刺激に影響されます。
自分自身をコントロールしたければ、自分をコントロールしている刺激の力を認識し、状況をコントロールすればよいのです。
ナポレオンは、死を覚悟して戦うために、副官に命じて自分が渡った橋を焼かせたそうです。
逃げ道を塞いで退路を断ってこそ、必死で戦い、勝利を得られることを知っていたからです。
図書館に行けば勉強をするしかなくなるし、発表を担当すると言って手を上げれば、しかたなく本を読むようになります。
逃げられない状況に自分を囲い込み、望みのことに没頭するための囲い込み技法です。
背水の陣で戦う人と、こっそり退路を作っておく人とでは、多くの面で違いがでます。
目の色も違い、態度や行動も違います。
その違いが、勝敗を分けます。
いかなるときも目標から目を逸らさない
テレビやパソコンのせいで勉強ができないのなら、それは勉強という目標から目を逸らしたから。
夜食の誘惑に陥ったのなら、ダイエットという目標から目を逸らしたから。
望むものがあれば、そこから目を逸らしてはいけません。
幸福な人は幸福な出来事と幸福になれる方法を考えながら時間を過ごします。
しかし。不幸な人は不幸な出来事、不愉快な人たちのことを考えながら、大部分の時間を過ごします。
子どもとの関係に悩んで相談に来た母親に、こんな質問をした。
「1日にどれくらい子どもについて考えていますか?」彼女は「ほとんど1日中、子どもについて考えています」と答えた。
具体的にどんなことを考えているか確かめると、こんな答えが返ってきた。
「いったい前世になんの罪があって…」、
「よりによって、何故あんな子が自分の子として生まれたのか…」、
「あの子さえいなければ…」私は彼女に、子どもとよい関係を作りたければ、それが実現するようなことを考えるべきだと言って、次のようなことについてどれほど考えるかを再び聞いた。
「自分がまだ知らない我が子の長所はなんだろうか?」、
「この子との壁を壊すために自分ができることはなんだろうか?」、
「我が子が自分から聞きたい言葉はなんだろう?」私の話を聞いていた彼女は、ため息をついて「そんなことは考えこともありませんでした」と言った。
(本書より)
望むものを手に入れたければ、望まないこと、避けたいことについてではなく、望むものとそれを手に入れる方法について考える時間をもっと増やすことです。
「障害物は、あなたが目標から目を逸らした時に現れるものだ。
目標に目を向けていれば、障害物は見えない。」
目標について、考えて考えて考える。
目的意識を持って生きるというのは、目的だけを考えて他のことをしてはいけない、ということでありません。
映画を観るという予定があるのであれば、映画は思いっきり楽しむ。
その映画を目標達成にどう活かせるのかを考えながら、楽しむ。
どこで誰と何をしていようと、それを目標と関連付けて手助けにするのです。
目標から目を逸らさないためには、刺激が必要です。
本の中では3つの刺激が挙げられていました。
私が新しいと思ったのは言語的・常識的触発刺激です。
百科事典の営業マンから、財界トップ30位に入るウンジングループを率いる立場にまで上り詰めた尹錫金(ユンソックム)会長は、毎朝「わたしの信条」を読み上げることから一日を始めるそうです。
言葉を浴びせること、目にいれることにより常に意識させるという刺激方法です。
私はこの本を受けて、以下のことを実行します。
| 何をやる? | どうやってやる? | いつやる? |
|---|---|---|
| 自分に適切な問いを投げかける | 問題について、最低3つの切り口で質問を自分に投げかける。 | 問題や課題に取り組む時 |
| 目標、できなかった時の代価を明らかにする | ・朝の早起き ・オーストラリア移住のための準備 この2つについて、期限と代価を決めて、インスタで公開する | 7/21の朝時間に期限と代価を決め、7/22に投稿する。 |
| 人生は実験の連続マインドを育てる | 1日3つ、いつもと違うことをする。 前日の夜に何を変えるか決めて、結果の仮説を立てる。 夜結果を考察する。 | 今日から! |
| 人に助けを上手に求める | 今自分が何について人に助けを求めるべきかを考える。 8月中にコンタクトを取り、助けを求める。 | 7/28の朝時間 助けを求めるべきものと、誰に助けを求めるかを考える。 |
| 自分をコントロールできない状況で挑戦する | 副業を進めるために、カフェに行く。 | 夫と相談し、月に1回土日に3時間の作業時間を確保する。 |
| 言語的・常識的触発刺激を取り入れる | 毎朝「私の信条」を読み上げる。 | 週末(7/19,朝ノート時間)に「私の信条」を作る。 来週月曜(7/21)の朝、鏡を見ながら読み上げる。 |
これを公開することも、一種の刺激です。
このあとこの内容を自分のノートに書き写し、スケジュール帳に未来予約します。
最後に
上に挙げた以外にも、学びになる方法はたくさんありました。
また、いつも野口さんがおっしゃっている自分を設定する、開始の締め切りを作るなどについても載っており、「美女ごっこだ〜」と思いながら読んでいました。
また、このような本は西洋の方が多いかと思いますが、お隣の韓国の方の本なので、
「あ、韓国でもこういうこと言うんだ」、「韓国ではそういう風に見られているんだ」という観点でも面白かったです。
今回の本👇️

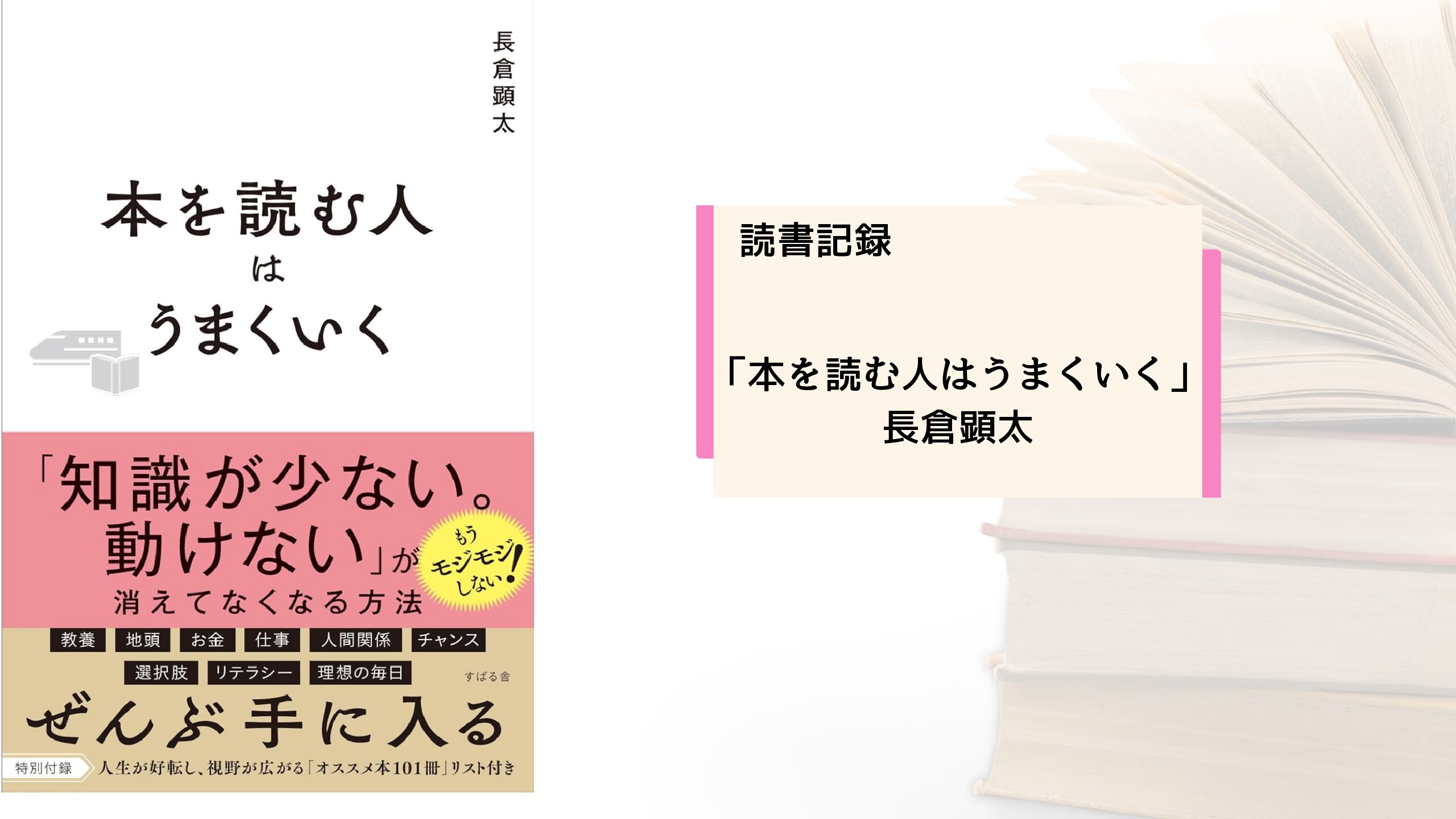

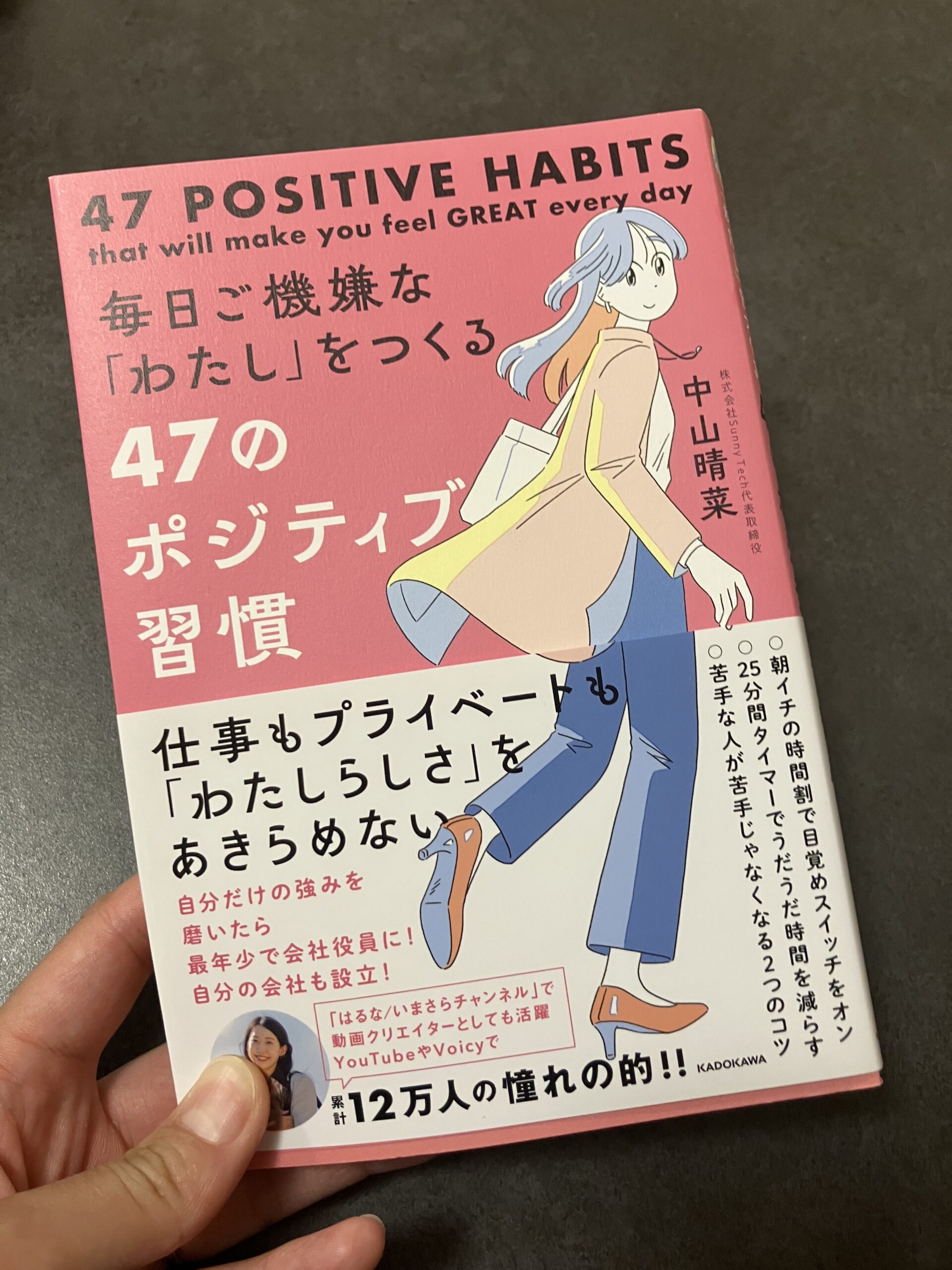

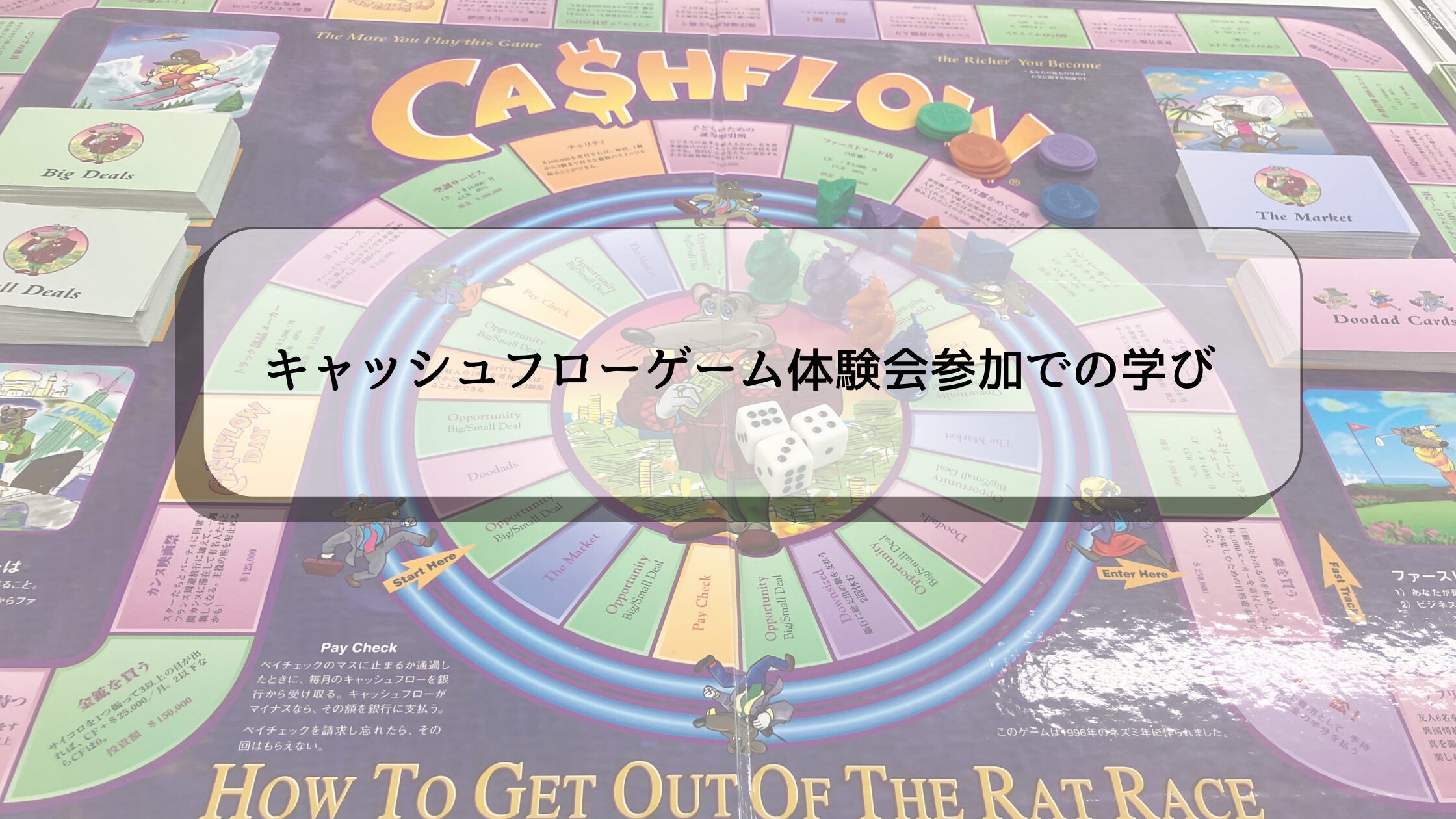

コメントを残す